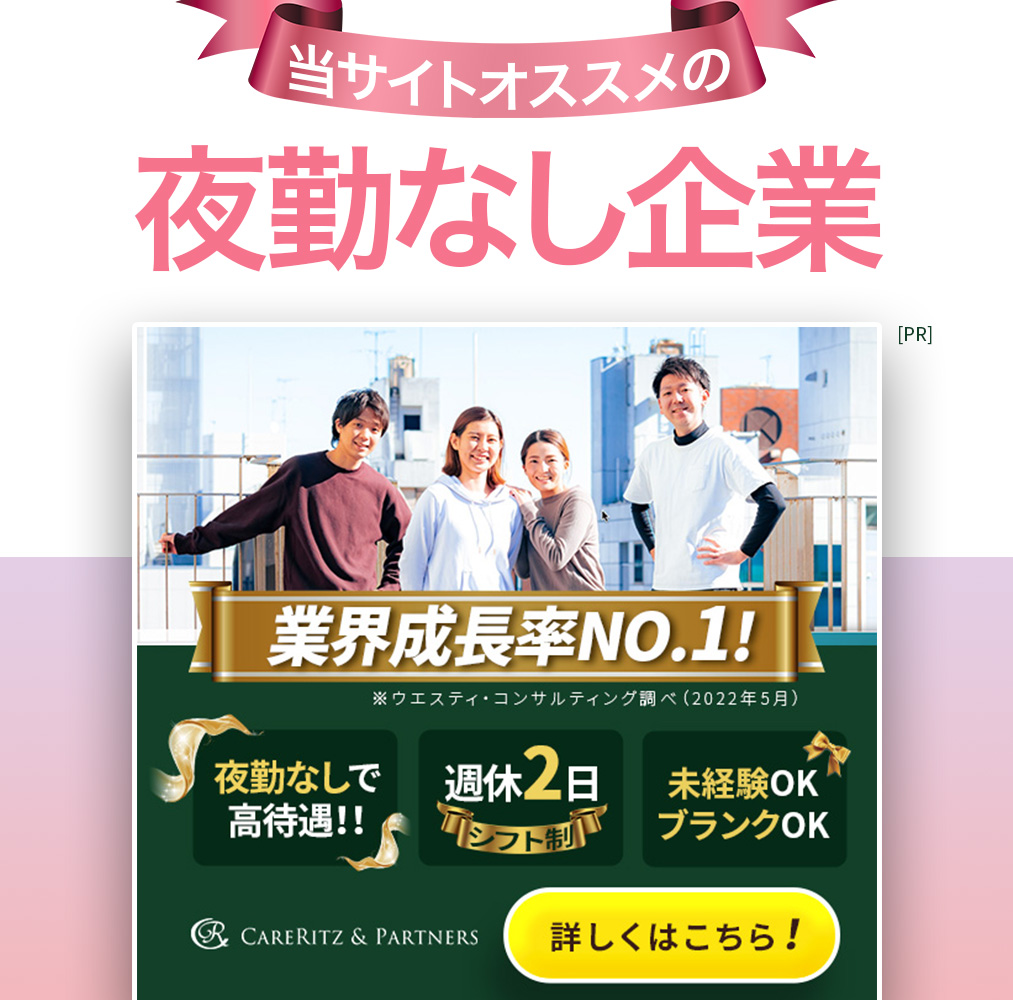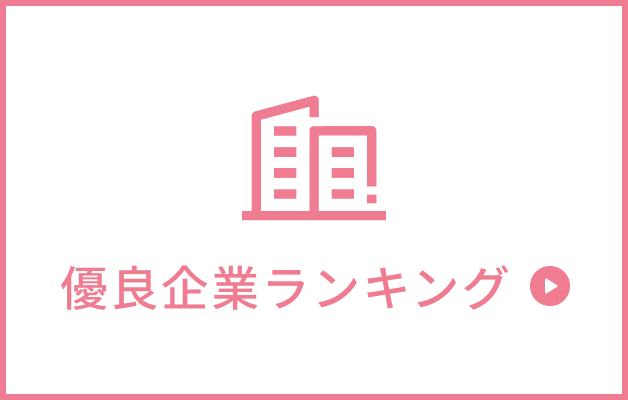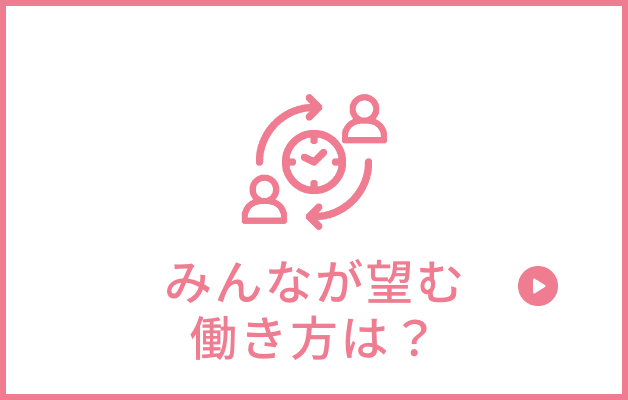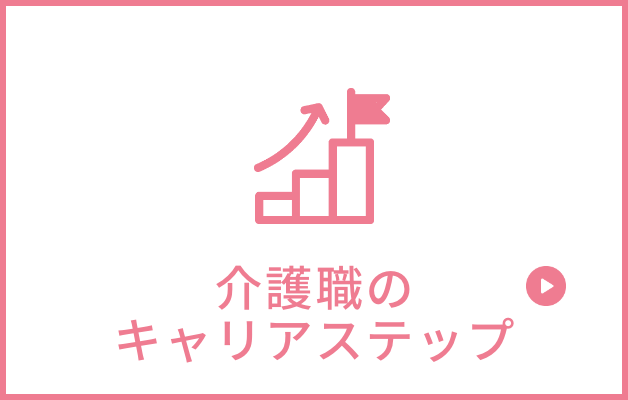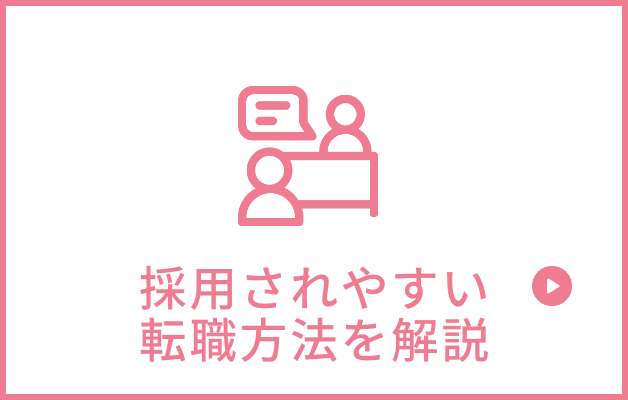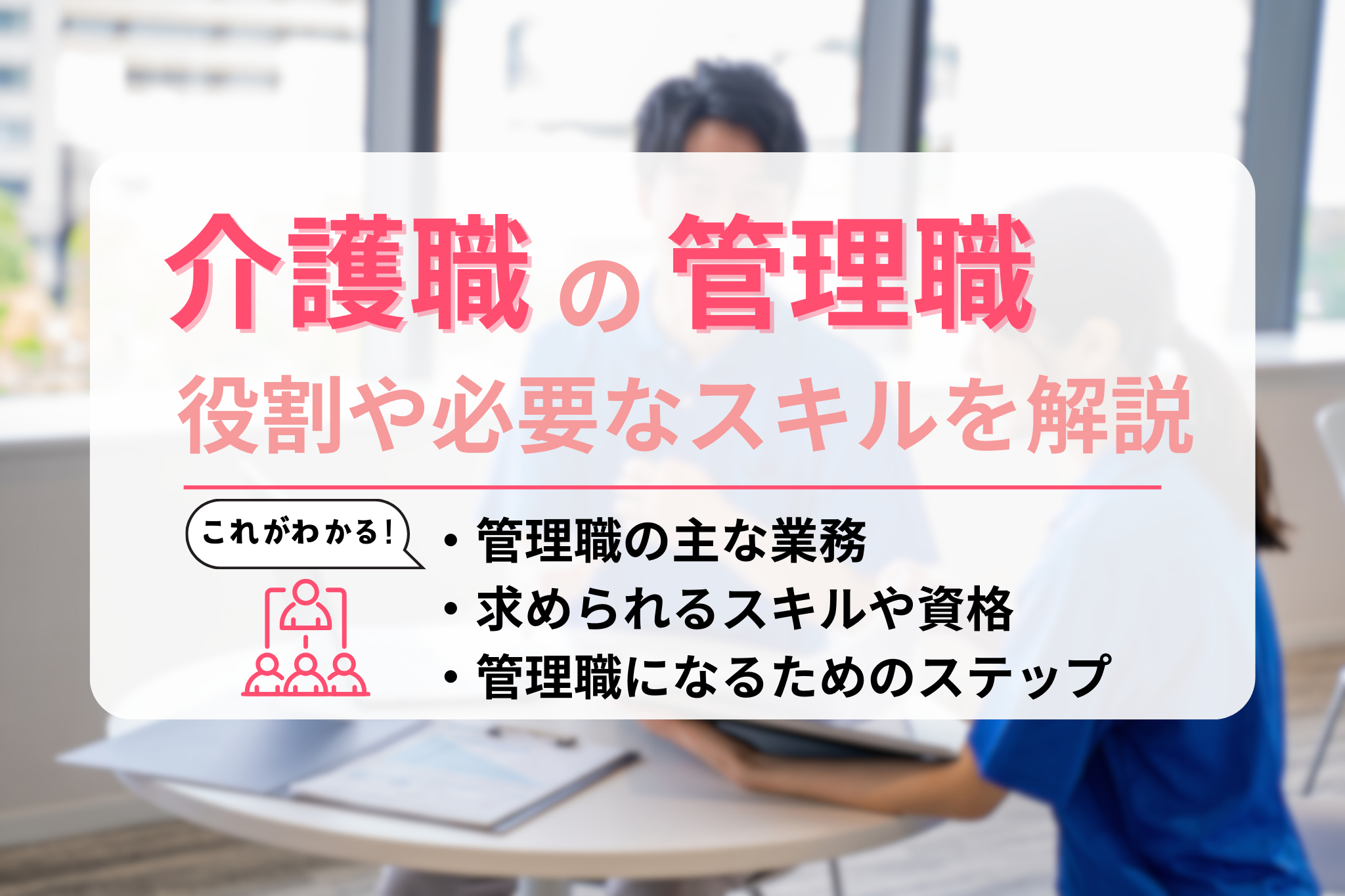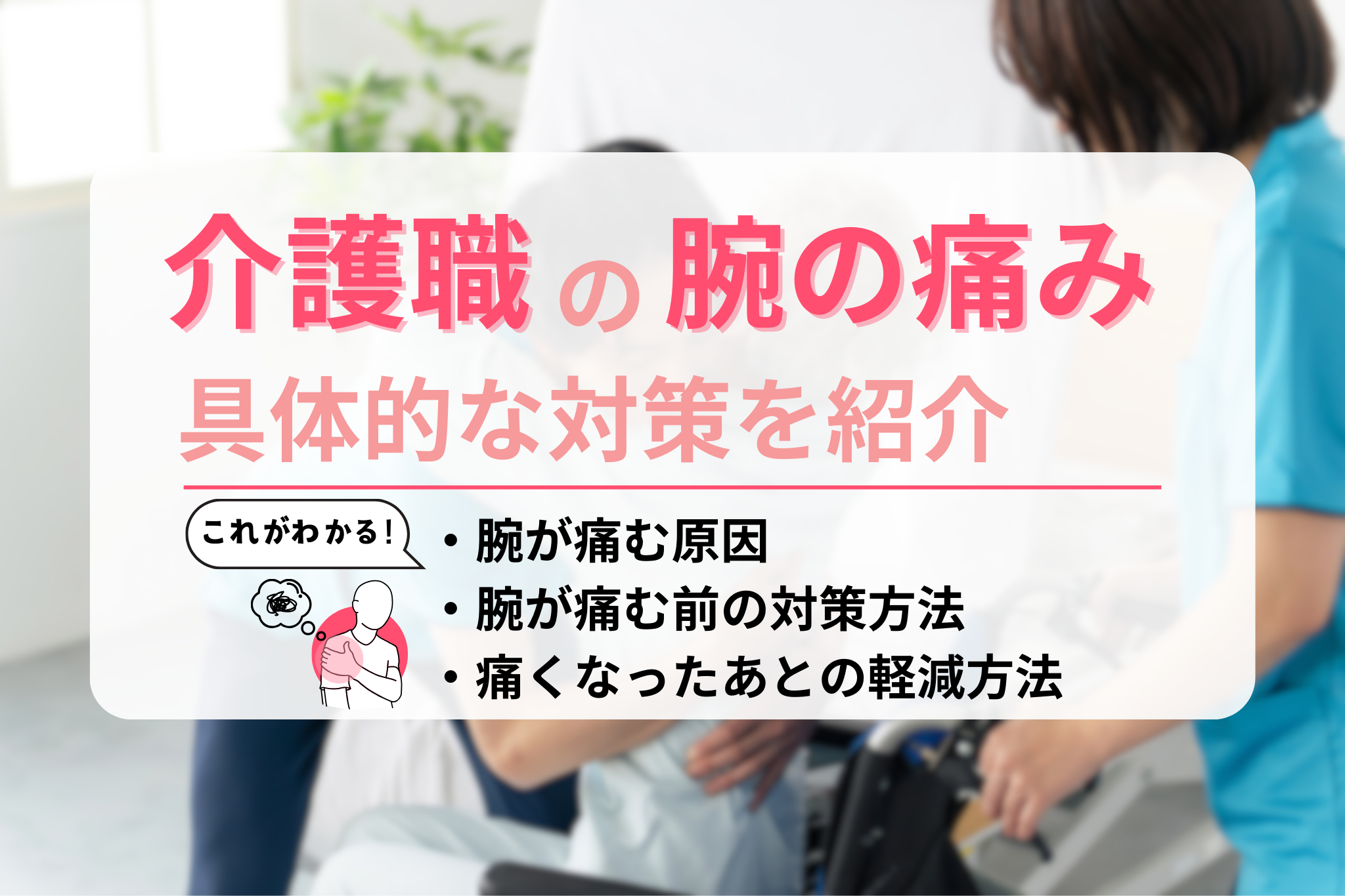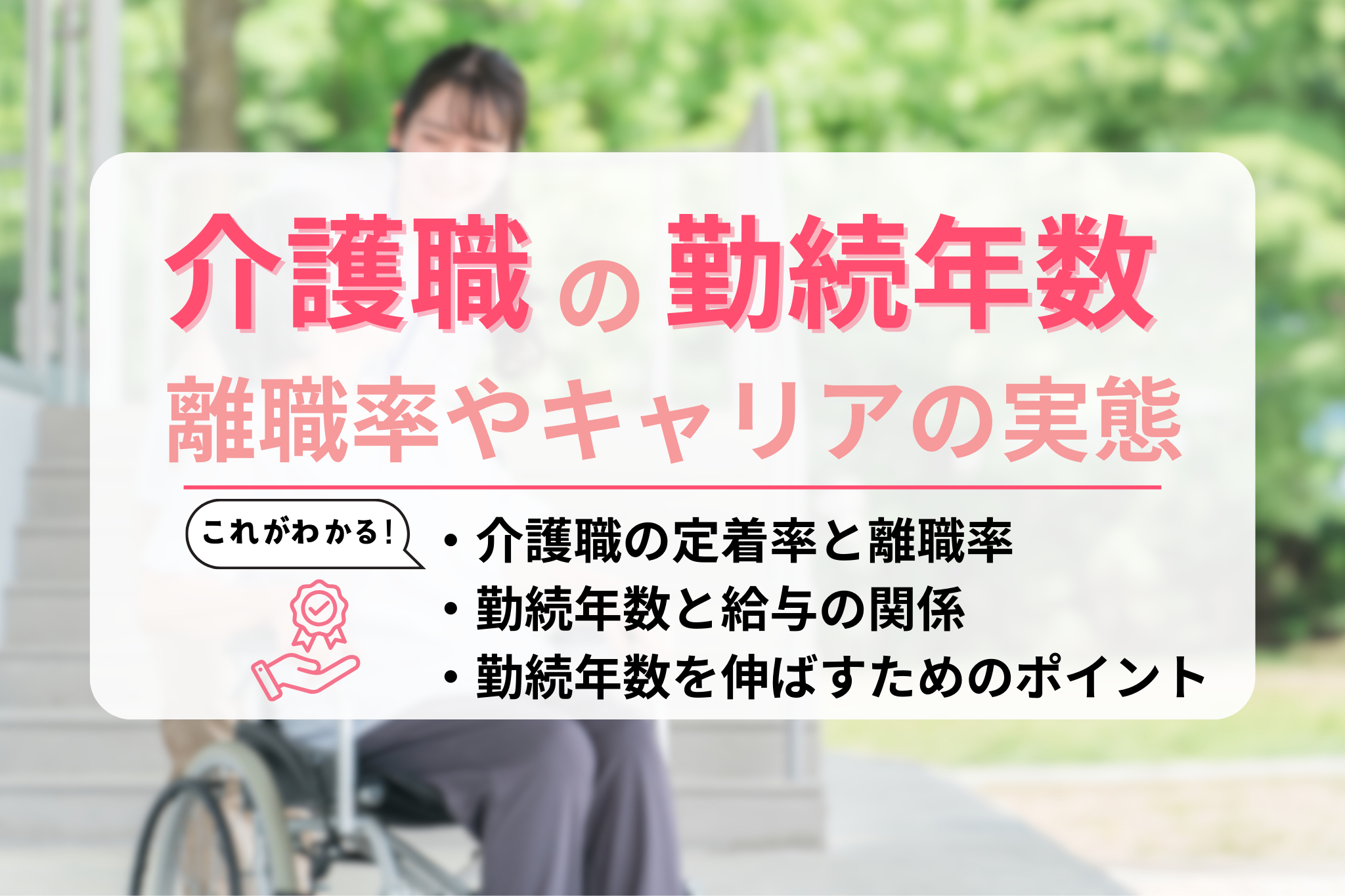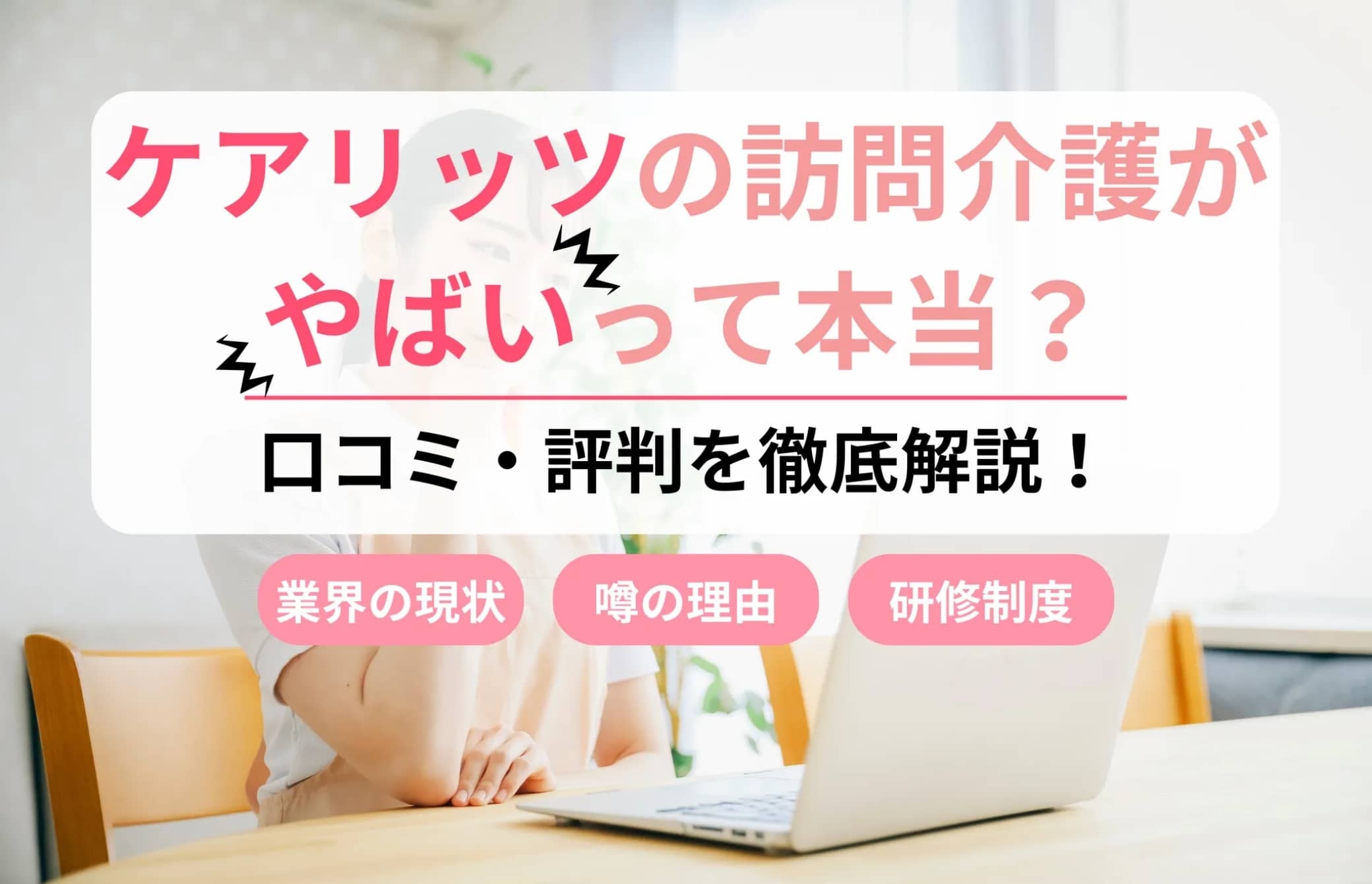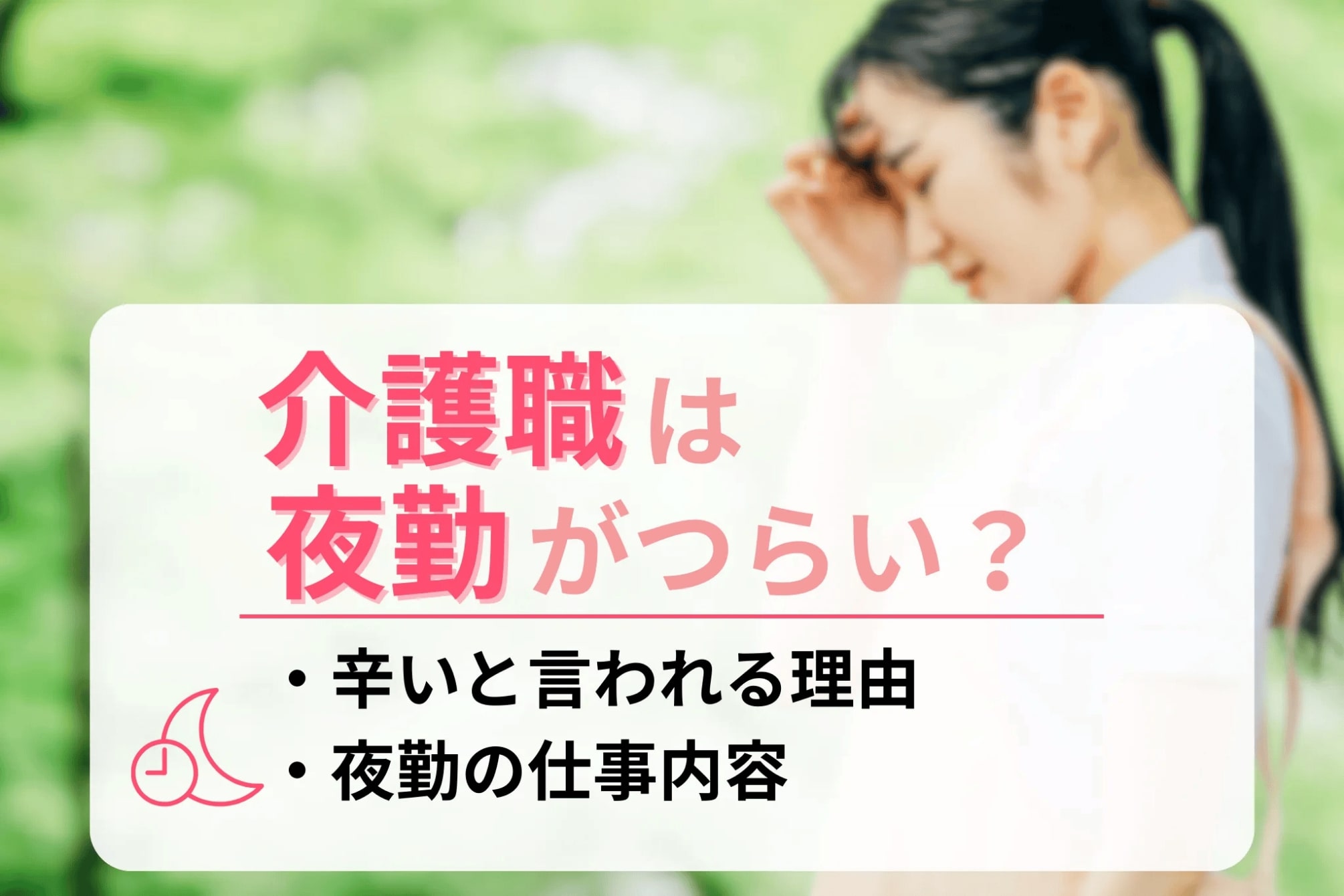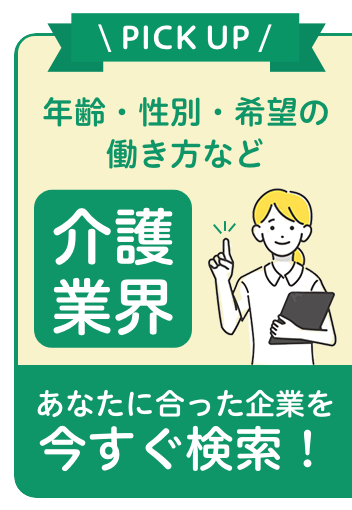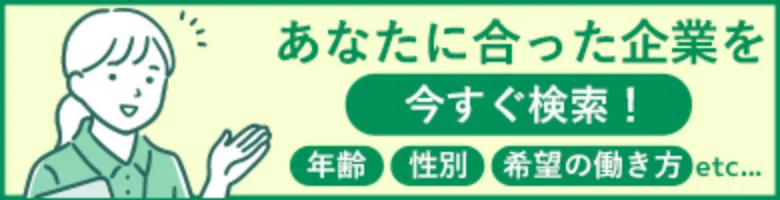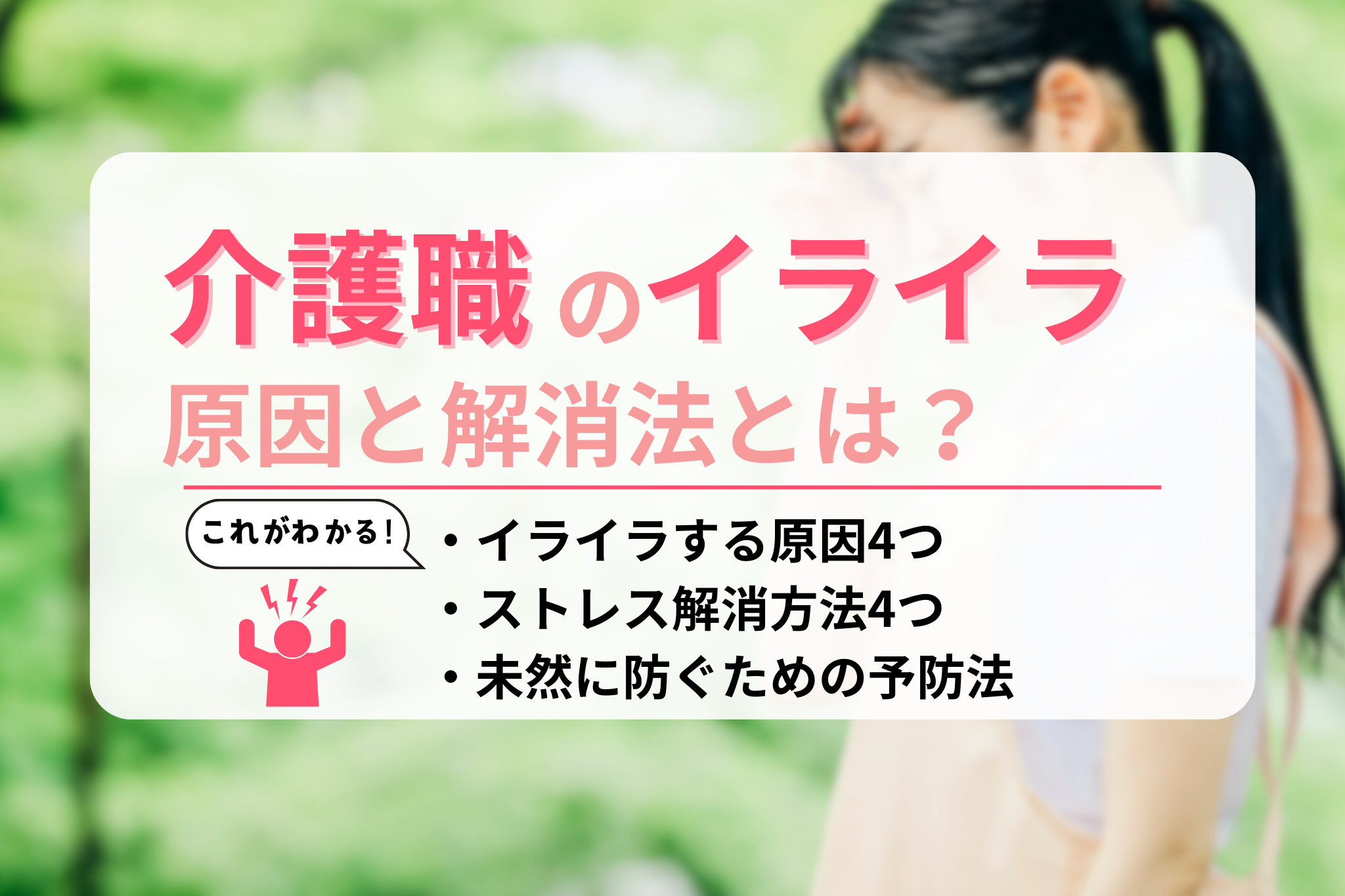
介護職は、利用者に寄り添いながら生活を支える重要な役割を果たしています。しかし、多くの介護職員が日々の業務の中で「イライラする」「ストレスが溜まる」と感じることがあります。特に、利用者やその家族との関係、同僚との人間関係、労働環境など、さまざまな要因が絡み合ってストレスの原因となります。
この記事では、介護職におけるイライラの原因を深掘りし、その解決策や予防策を具体的に提案します。さらに、どうしても改善できない場合の選択肢として転職についても考察し、介護職員としてのキャリアを前向きに進めるためのヒントをお届けします。
介護職でイライラするよくある原因4つ
介護職員のストレスと考えられる主な原因4つを紹介します。
| 原因 | 具体例 | 対策 |
|---|---|---|
| 1. 利用者とのコミュニケーションギャップ | ・認知症の方との意思疎通の難しさ ・同じ説明の繰り返し |
・利用者の背景理解 ・コミュニケーション技術の向上 |
| 2. 同僚や上司との人間関係の悩み | ・業務配分の不公平感 ・意見の対立 |
・オープンなコミュニケーション ・チームビルディング活動 |
| 3. 業務過多や労働環境のストレス | ・人員不足による負担増 ・時間内に業務が終わらない |
・業務の優先順位付け ・効率的な作業方法の導入 |
| 4. 夜勤やシフトの不規則さが招く疲労 | ・生活リズムの乱れ ・慢性的な睡眠不足 |
・適切な休息の確保 ・シフト管理の最適化 |
1. 利用者とのコミュニケーションギャップ
介護の現場では、利用者とのスムーズなコミュニケーションが重要です。しかし、高齢者や認知症の方とのやり取りでは、思ったように話が通じなかったり、何度も同じ説明を繰り返す必要がある場合があります。
さらに、利用者が介護職員に対して不満を抱く場合もあり、否定的な態度を取られることがあります。こうした状況は、職員の精神的な負担を増やし、イライラや不安を引き起こします。
この問題を解消するには、利用者の気持ちや背景を深く理解する姿勢が必要です。例えば、利用者が何を不安に思い、どのような支援を望んでいるのかを知ることで、関係がスムーズになることがあります。最新の研究では、認知症の方とのコミュニケーションにおいて、非言語的な手法(ジェスチャーや表情)の重要性が指摘されています。
2. 同僚や上司との人間関係の悩み
職場での人間関係も、介護職のイライラの大きな要因です。特に、上司との相性が合わない、同僚との意見が対立する、といった状況では、ストレスが溜まりやすくなります。
さらに、チームでの業務配分が不公平だと感じる場面も、イライラを増幅させます。例えば、ある職員に負担が集中している場合、周囲との信頼関係が崩れることもあります。
ここで、公益財団法人介護労働安定センターが介護職の離職理由を調査した結果を紹介します。
| 退職理由(複数回答) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家族の介護・看護のため | 3.40% | 4.10% | 4.90% | 5.00% | 4.50% |
| 結婚・妊娠・出産・育児のため | 13.30% | 20.40% | 19.90% | 8.20% | 8.40% |
| 病気・高齢のため | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.40% | 3.10% |
| 定年・雇用契約の満了のため | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.30% | 3.10% |
| 家族の転職・転勤、又は事業所の移転のため | 1.70% | 1.40% | 1.70% | 1.60% | 1.70% |
| 法人や施設・事業所の理念や 運営のあり方に不満があったため |
8.60% | 8.80% | 8.20% | 8.30% | 7.80% |
| 職場の人間関係に問題があったため | 23.20% | 34.30% | 26.80% | 26.30% | 19.90% |
| 自分に向かない仕事だったため | 6.60% | 6.80% | 6.70% | 7.10% | 7.60% |
| 自分の将来の見込みが立たなかったため | 16.20% | 16.40% | 16.50% | 15.80% | 13.20% |
| 収入が少なかったため | 16.60% | 16.00% | 16.40% | 16.60% | 16.00% |
| 新しい資格を取ったから | 7.60% | 9.80% | 7.70% | 7.60% | 5.90% |
| 他に良い仕事・職場があったため | 19.90% | 17.00% | 16.90% | 19.00% | 16.00% |
| 人員整理・勧奨退職・法人解散・事業不振等のため | 9.70% | 9.60% | 9.80% | 9.90% | 7.60% |
参考:公益財団法人介護労働安定センター『令和5年度 介護労働実態調査結果』
この調査結果を見ると、介護職を退職した人の約5人に1人が「人間関係」を理由に退職していることがわかります。こうした状況を改善するには、職場内での円滑なコミュニケーションが不可欠です。また、自分の感情を適切に伝えるスキルを身につけることで、問題解決に繋がることがあります。
3. 業務過多や労働環境のストレス
介護職は、多岐にわたる業務を限られた時間内でこなさなければならないことが多く、これがストレスの大きな原因となります。さらに、人員不足の職場では、一人当たりの負担が増加し、疲労感が溜まりやすくなります。
業務過多によるストレスを軽減するには、業務の優先順位を整理し、効率的に進める方法を模索することが重要です。また、職場全体で業務負担を平等に分担する仕組みづくりも必要です。最新のAI技術やIoTデバイスを活用した業務効率化も、注目されている解決策の一つです。
4. 夜勤やシフトの不規則さが招く疲労
介護職において、夜勤や不規則なシフト勤務は避けられない課題です。これにより、生活リズムが乱れ、疲労感が蓄積することが多々あります。特に夜勤明けの体力回復が間に合わないまま日勤に入ると、心身のバランスを崩しやすくなります。
シフト勤務の疲労を軽減するためには、十分な休息を確保し、バランスの取れた食事や適度な運動を心掛けることが重要です。また、シフト管理を職場全体で見直し、適切な勤務体制を確保することも求められます。2024年の最新研究では、サーカディアンリズムに配慮したシフト設計の重要性が指摘されています。
介護職のイライラを解消する方法4つ
1. 感情をコントロールするマインドフルネスの実践
マインドフルネスとは、現在の瞬間に集中し、感情を冷静に受け止める方法です。介護現場での緊張やストレスを和らげるためには、深呼吸や瞑想を日常に取り入れることが効果的です。
例えば、業務の合間に3分間だけ深呼吸に集中する時間を作ると、気持ちが落ち着き、次の業務に前向きに取り組むことができます。これを習慣化することで、感情のコントロール力を養うことができます。最新のアプリケーションを活用したマインドフルネス実践も注目されています。
2. ストレス発散に効果的な趣味やリフレッシュ法
日常的にストレスを発散する方法を見つけることは、介護職として働く上で欠かせない要素です。趣味やリフレッシュ方法を取り入れることで、仕事以外の時間を充実させ、心身のバランスを保つことができます。
たとえば、お気に入りの音楽を聴くことで、心を落ち着ける効果が期待できます。特にリラックス効果のあるクラシック音楽やヒーリングミュージックは、介護職の疲れた心を癒すのに最適です。適度な運動もストレス発散だけでなく、身体の健康維持にも効果的です。
3. 勇気を出して同僚や上司に日々相談する
職場で直面する問題を一人で抱え込むことは、ストレスを増大させるだけでなく、解決を難しくしてしまうことがあります。そのため、日常的に同僚や上司に相談する習慣を持つことが、問題解決の近道となります。
相談することで、自分では気づけなかった視点や解決策を得られることがあります。例えば、同僚が過去に似た問題に直面していた場合、その経験からアドバイスをもらえる可能性があります。また、上司に相談することで、職場の体制やシステムの改善につながることもあります。
4. 職場環境を改善する提案力を身につける
職場での改善提案を行うことも、ストレス軽減に繋がります。具体的なアクションとして、「新しいケア方法の導入」や「効率的なシフト体制の提案」などが挙げられます。
介護職の業務は身体的にも精神的にも負担が大きく、特に人手不足やシフトの不均衡などが問題になることがあります。このような課題に対し、具体的な改善案を提案することで、自身の働きやすさが向上し、同僚にもポジティブな影響を与えることができます。
提案を実現するためには、関係者との話し合いが重要です。反対意見にも耳を傾け、柔軟に提案内容を調整することが成功のカギとなるでしょう。
イライラを未然に防ぐための対策3選
1. 明確なキャリアプランを立てて働くモチベーションを維持
介護職としてのキャリアを計画的に進めることで、仕事に対するモチベーションが高まり、イライラを未然に防ぐことができます。2024年の介護業界では、専門性の高い資格取得やマネジメントスキルの向上が重視されています。
2. 信頼できる同僚や相談相手を作る
職場で信頼できる仲間を作ることで、日々の業務がスムーズになり、ストレスが軽減されます。最新の研究では、職場内のソーシャルサポートがメンタルヘルスに大きな影響を与えることが明らかになっています。
3. 仕事を忘れられる趣味や習慣を作る
仕事以外の時間を楽しむために、自分の興味を活かした趣味や活動を見つけることが大切です。2024年のトレンドとして、オンラインコミュニティを活用した新しい趣味の発見や学習が注目されています。
介護職でイライラを感じたら転職も検討しよう
人間にはどうしても相性というものがあり、自分に合わない人間や職場環境は必ず存在します。他の人にはイライラしない状況でも、自分にとってはイライラしてしまう環境が溢れている職場というのも珍しくありません。例えば、仕事の後の飲み会がストレス発散になる人もいれば、逆にストレスの原因になる人もいます。どうしても環境が合わないと感じた場合は、思い切って転職するのも選択肢の一つです。
- 自身の安全と健康を最優先に考える
- キャリアプランを再考し、新たな環境を探す
- 転職エージェントや介護職専門の求人サイトを活用する
- 面接時に職場の雰囲気や人間関係について質問する
転職は大きな決断ですが、自身の成長と健康のためにも、常に選択肢として自分の中に持っておくことが大切です。
転職の適切なタイミングを見極める
転職を検討すべきタイミングを見極めるには、以下のポイントを確認することが重要です。
- 身体的・精神的な負担が大きすぎる場合
- キャリアアップのチャンスが限られている場合
- 職場の人間関係に問題がある場合
- 業界のトレンドが変わってきている場合
現在の職場で改善が見込めない場合、新しい環境での挑戦を検討してみましょう。昨今の介護業界は働き方改革が進み、ICTを積極的に取り入れるなど柔軟な働き方を提供する事業所が増えています。
良い職場を見つけるための企業選び
介護職で働く上で、職場環境や企業文化は自身のストレスへ大きな影響を及ぼします。良い職場を見つけるには、単に給与や労働時間だけを重視するのではなく、自分に合った雰囲気や働き方を見極めることが大切です。
例えば、退職金制度や資格取得支援制度、住宅手当など、働き続ける上で役立つ制度があるかを確認してください。
そして、勤務時間や休暇の取りやすさも特に重要となります。求人情報に「働きやすい環境」などと記載されていても、実際の状況は異なる場合があるため注意が必要です。夜勤がある職種かどうかなど、自分の理想のワークライフバランスを保つためには必見の項目です。
転職後にストレスを減らすポイント
新しい職場での適応は、転職後のストレスを軽減するための重要な要素です。以下のポイントを意識することで、環境に慣れやすくなり、職場での満足度を高めることができます。
- 環境に慣れることを優先
- 良好な人間関係を築くためにも工夫する(しっかり感謝を伝えるなど)
- 自己成長の意識を持つ
環境を変えることは、自身が想像するより膨大なストレスが生じます。転職直後から結果を出そうと焦るよりも、まずは新しい環境になれることを最優先にしましょう。
まとめ
介護職におけるイライラは、日常の中で原因を正確に把握し、適切な対策を講じることで大幅に軽減できます。ストレスの原因は一人ひとり異なりますが、コミュニケーションの改善、作業負担の分散、そして自分自身のケアが鍵となります。
イライラを放置してしまうと、うつ病や抑うつ状態を引き起こす原因にもなってしまい、結果的に休職に追い込まれるケースもあります。どうしても対策が講じれない場合は、環境を新しくすることを検討しましょう。
当サイトについて
当サイトでは、自分に合った介護業界の企業を検索したり、ランキング形式で各社を見ることが出来ます。
年収や口コミ、福利厚生など、あらゆる面から比較しているので、介護業界の正社員として働きたい方も、ぜひご活用下さい!

あなたにとっての最高の職場は?
自分に合った企業を検索!
当サイト独自の調査結果を元に、あなたに合っ た企業をご紹介!!理想の働き方や条件から今す ぐ検索!
条件から検索
\年収や口コミ、福利厚生などで徹底比較!/